国際会議の冒頭、米国人の同僚が笑顔で「Hi, Yamada-san!」と呼びかけてきたとき、どこか違和感を覚えたことはありませんか?
日本ではごく自然な敬称「〜さん」。でも、それをそのまま英語に持ち込むと、少し不自然な空気が流れることがあります。
名前の呼び方は、単なる習慣やマナーを超えて、「文化の違い」そのもの。相手との距離感、関係性、そしてビジネスにおける信頼構築に大きな影響を与えます。
日本式「〜さん」文化の背景
日本では、職場でも日常生活でも、苗字+「さん」で呼ぶのが一般的です。これは、相手への敬意と距離を同時に保つための文化的装置とも言えます。
- 苗字を使うことで、ある種の「公的な関係」を保つ
- 「呼び捨て=無礼」という感覚が強く根付いている
- 敬語文化と同じく、距離感・立場(上司・部下)を丁寧に表現する手段
そのため、下の名前(ファーストネーム)で呼び合う文化に直面すると、どう対応してよいか戸惑う方も多いのではないでしょうか。
米英式の「名前」や「ニックネーム」文化
呼び方ひとつで関係性が変わる
英語圏では、ビジネスの場でもファーストネームで呼び合うことが多い印象です。たとえ相手が上司やCEOでも、「Hi Mr. Smith」ではなく、「Hi, John」「Thanks, Mary」といった呼びかけが多い印象です。
一方、日本でCEOの山田太郎さんに、『やあ、太郎』と言えるのは、よほどの幼なじみか、酔っ払った同期くらいのものでしょう🤣🤣🤣
フォーマルな名前で呼び続けると、かえって“壁を作っている”と思われることもあるため、意識的にカジュアルな呼び方を求められる場面もあります。
欧州でのかなり根付いたニックネーム文化
ある出張で、同僚のMattと一緒にホテルのチェックイン時、予約名が「Matthew」になっていました。最初は別人の予約かと混乱しました。
その後、人事の資料などに触れる様な立場になった時、他の同僚たちも日常的にニックネームを使っていることが判明。例えば、RobertがBob、ElizabethがLizなど。公的な場(人事台帳やパスポート)ではフルネームが記載されており、日常ではニックネームを使うのが一般的でした。
これは英語圏では単なる略称ではなく、「親しみ」や「カジュアルな関係性」を示す重要な要素なのです。この経験から、欧州ではニックネームが広く浸透しており、ビジネスシーンでも日常的に使われていることを実感しました。
日本人にニックネームをつける:その是非
私が入社した頃(90年代)には、海外営業部では誰もが最初に英語のニックネームをつける習慣がありました。自分の名前の最初のアルファベットから、あるいは日本語の本名を短く呼びやすくする、などありました。
| 日本式 | 英語風ニックネーム | 補足・由来 |
| 透(とおる) | Ted | 頭文字のT。 |
| 健一(けんいち) | Ken | 直訳的ニックネーム |
| 拓也(たくや) | Taku | Takuはそのまま短縮形 |
| 良太(りょうた) | Leo | Ryoの発音が難しい代用 |
| 明(あきら) | Alex | Alexは語感・イニシャル一致。 |
| 恵美(えみ)千恵美(ちえみ) | Emi / Emily | Emiはそのまま。 |
| 知一郎(ともいちろう) | Tom | 長いので省略しつつも米英風 |
メリット
- 海外の同僚にとって覚えやすく、発音しやすい
- 会話がフレンドリーになり、距離が縮まりやすい
- “仲間”として受け入れられていると感じやすい
注意点・リスク
- 本人の意志に関係なく略されると違和感が残る
- 日本人同士から見るとカッコつけてる印象になることも
- 本名への愛着やアイデンティティが損なわれると感じるケースもある
自分の「呼ばれ方」を戦略的にデザインする
ただの「呼び方」とあなどるなかれ。英語圏では名前の呼び方がそのまま関係性に影響することもあります。だからこそ、自分の「呼ばれ方」を少しだけ意識しておくと、仕事がぐっとスムーズになります。
- 名刺やメール署名など一貫性を保つ。(例:Ted Yamada 山田透さんの場合)
- この場合、できればIT部門と相談し、初めからメアドも考慮すると良い。
- NG:メアドは、toru.yamada@XXXX.xomで、普段の呼び名がTedのケースでは、将来的に必ず、ted.yamadap@XXXX.comのメールが発信され、『送った&届かない問題』が発生します。私は同じ理由で何十通ものメールを紛失しました。その後、ITに依頼し、toru.yamadaとted.yamadaの
- 両方のメールが同じメールボックスに着信する手配をしてもらいました。(名称はFictionです)
- 会議の冒頭で「Call me Taro」と自然に伝える
- 相手が自分をどう呼んでいるかに注意を払い、心地よくない場合は丁寧に修正する
日本人同士の呼び方:ファーストネーム+さんのジレンマ
日本人が日本人を呼ぶ際、特に上司に対してファーストネームを呼び捨てにするのは気が引けるものです。そのため、ファーストネーム+さん(例:Taro-san)という呼び方が一般的です。
しかし、これを真似て欧米人も「Taro-san」と呼ぶことがあります。本人としては「Taro」と呼ばれたいと思っていても、「-san」が付くことで距離を感じてしまうジレンマが生じることがあります。
このような場合、自分がどのように呼ばれたいかを明確に伝えることが大切です。
まとめ:呼び方は文化理解と自己発信の橋渡し
名前の「呼び方」は、単なるラベルではなく、文化を映す鏡であり、自分自身をどう位置づけるかのメッセージでもあります。
だからこそ、相手の文化を尊重しながらも、自分がどう呼ばれたいかを丁寧に設計し、必要に応じて発信していくことが、信頼関係を築くうえで大きな意味を持ちます。
- 日本の「〜さん」文化は敬意と距離感を重視した繊細なバランスを持つ
- 欧米ではファーストネームやニックネームで親しみを表現するのが一般的
- 自分の呼ばれ方は、受け身ではなく、戦略的に設計して伝えることができる
- 呼び方のズレは、誤解や距離感につながることもあるため、柔軟に修正していく姿勢が大切

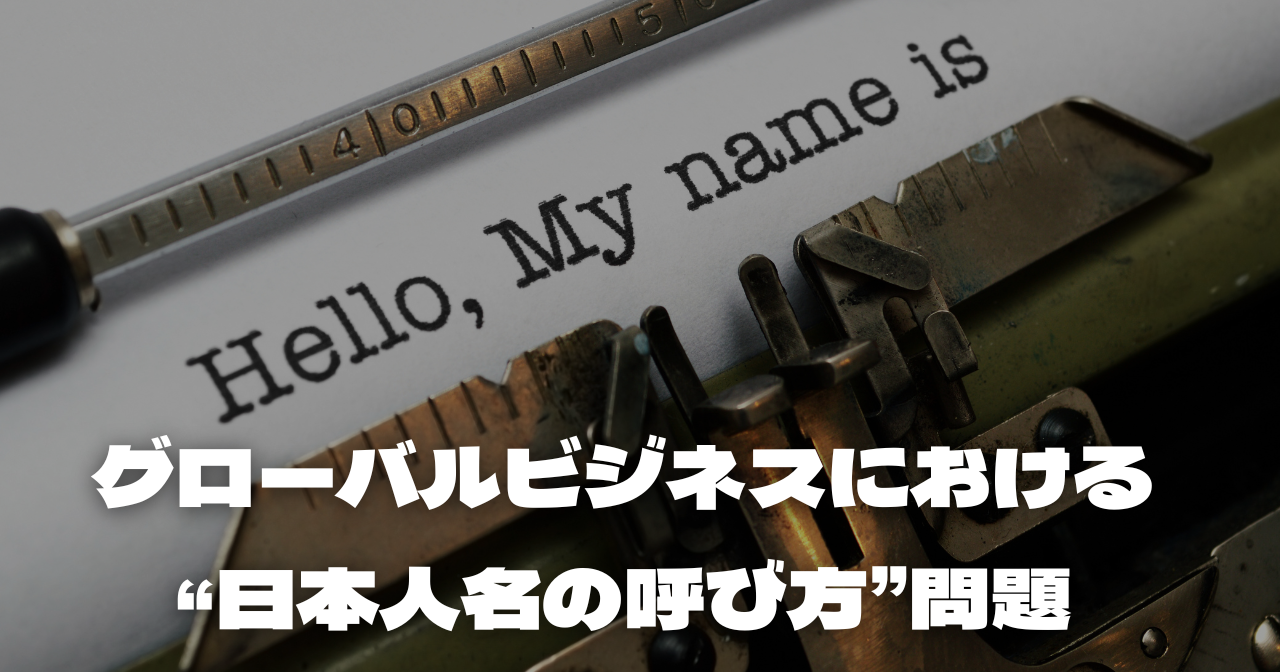
コメント