ビジネス英語を使う中で、「伝えたつもり」と「伝わり方」のギャップに気づく瞬間が何度もあります。特に、使用頻度が高い簡単な中学生英語でありながら、それを日本的な感覚で使うと、意図しないニュアンスになってしまうことが少なくありません。
日常生活ならまだしも、ビジネス現場において、時にそれは大きな痛手に発展してしまうことも・・・。今回は、私自身の経験を交えながら、誤解を生みやすい英単語やフレーズを紹介し、どのように使い分けるべきかを解説します。
Interesting(微妙…?)
我々はついつい「面白そう」「いいですね」の意味をこめて interesting を使ってしまうことがないでしょうか。英語の interesting は、その意図通りの「興味深い」という意味だけでなく、「評価しづらい」「微妙」といった意味合いも含まれることがあります。

ついつい「なるほど」のつもりで 『That’s interesting.』を連発していたところ、英国人の上司から『それは Good interesting なのか? Bad interesting なのか?』と尋ねられたことがありました。そのとき初めて、自分が意図しているニュアンスと英語の使い方がズレていることに気づきました。
ネイティブの人たちは、発音時のイントネーションはもちろん、顔の表情や仕草などでも使い分けてる感じがします。
慣れない日本人が行うとさらに誤解を招くおそれがあるので、本当にポジティブに伝えたい場合は、That’s great! や That’s fascinating! などの表現を使うほうが間違いないと言えそうです。
Understand(理解した…だけ?)
日本では、相手の発言を受けた際に「わかりました」という言葉をよく使います。これは単に「内容を把握しました」という意味合いで使うこともあれば、「合意です」と同意のニュアンスを含むこともあります。
例えば、会議で上司の意見を聞いたときに「わかりました」と同意の意を暗に伝えることがあります。
しかし、英語の I understand. は「相手の意見を理解した」だけの意味にとどまり、必ずしも同意しているわけではありません。

「わかりました、承知しました」という意味で何度か 「I understand.」と答えていたところ、これも同じ上司から、微笑みながら「So, you understood but not agree?(理解はしたけど、賛成はしてないってこと?)」と言われ、ハッとしました。
- I understand your point. → 頭で理解しただけ
- I fully agree with your proposal. → 明確な同意
意見に完全同意する場合は、completely, fully, totally, hundred percent などを一緒に使って強調されます。明確な意思表示は誤解を防ぐことができます。
Consider(検討はするけど?)
日本語の「検討します」は前向きな響きがあります。(修飾語として「前向きに」がワンセットで使われますよね!)
グローバル・ビジネスシーンにおいて「I will consider it.」と述べる場合、これは提案や依頼に対して同様に「検討します」という意味になります。
しかし、この「検討する」は、必ずしも実行を約束するものではありません。提案を慎重に考慮することを示しています。
そのため、日本の「どちらかと言うと実行する可能性が高い」とは若干ニュアンスが異なり、「考慮はするが、実行するかどうかは未定」という意味合いが強いです。
実行確率(低→高)の順番で並べると:
実行確率が高い表現としては以下があります。
| 表現 | 意味 | 実際のニュアンス | 実効可能性 |
| I will consider it. | 検討します | 実施する確率は低〜中程度 | 考えるが保証はないレベル |
| I will look into it. | 調べてみます | 検討よりその後の行動が少し具体的になる | まだ不確定要素が多い |
| I will review it carefully. | しっかりと見直します | 真剣に考える姿勢は示している | が、実行が決定的ではない |
| I will follow up on this. | 後ほど具体的に対応します | 具体的にアクションを示唆し前向き | 比較的実行性が高い |
| I will make it a priority. | 優先的に取り組みます | 実行に向けて積極的 | 実現可能性がかなり高い |
| I will get this done. I will move forward with this. | これを進めます 実行します | 実行に向けて積極的 | 実現可能性がかなり高い |
Suggest(提案、それとも指示?)
日本語で「提案します」というと、「よければ〜してみてはいかがでしょうか?」という控えめな響きがあります。
ところが、英語の「I suggest…」は、話し手と聞き手の関係性や文脈によってニュアンスが違ってきます。
単なる「提案」を超えて「こうすべきである」という強い推奨や指示的なニュアンスを含むことがあります。特に、上司が部下に対して使った場合、「指示」に近くなる可能性が高いと言えます。

上司の文面に「I suggest…」とあったのに対し、「ああ、ヒントをくれたんだな。感謝、感謝。」レベルで受け取りつつ、別案を考えていたところ、「この間の案件、いつやるのか?」と確認されました。
「I suggest」 は、「You should」よりは柔らかい印象ですが、上司が使う場合には、部下は「推奨」よりも「事実上の指示」として捉える可能性が十分あります。
例えば、以下のようなシチュエーションです。
- 上司:I suggest we update this document by tomorrow morning.
(この書類は明日の朝までに更新したほうが良いと思う。)
日本語の感覚で言えば単なる提案のようにも聞こえますが、実際には上司が言うと部下は「明日朝までに更新する必要がある」と強く受け取る可能性があります。
同じ文面でも、逆に部下が上司に対して使うと、あくまで「柔らかな提案」というニュアンスになります。
英語では、以下のようにニュアンスを調整することができます。
- 提案を柔らかく伝えたい場合:
Maybe we could… / How about…? - 指示的な意味を明確に伝えたい場合:
We need to… / Please make sure to… / I strongly recommend…
「I suggest」は状況次第で「提案」から「軽い指示」まで幅広いニュアンスを持ちます。受け取り側の立場や文脈を考え、適切な強度の言葉を選ぶ必要があります。
Fine(問題ない?悪くない?)
日本人の多くは、英語授業の 「How are you?」「I am fine. Thank you, and you?」という定型文を覚えているのではないでしょうか。
このため、多くの日本人は「fine」を「元気です」「素晴らしい」「とても良い」という積極的で肯定的な意味だと認識しています。
しかし、「Fine」は英語圏では、以下のようなニュアンスで使用されることが多いです。
- 「まあ悪くはない(けれど特に良いわけでもない)」
- 「最低限OKです(積極的には評価していない)」
- 「これで問題ないけど、本音を言えばもう少し良い方が嬉しい」
つまり「fine」は「積極的な肯定」というより、「消極的な肯定」に近いのです。
例えば、会議でプレゼンの案を共有した際、上司や同僚が「That’s fine.」とコメントした場合、それは「問題はないが、特に優れているとも思っていない」という意味かもしれません。我々が使う際も、「いいですね」の感覚で fine を使うと、意図とは異なり、相手に冷淡な印象を与えてしまう可能性があります。

同僚がある資料を仕上げた際に「What do you think?」と聞かれ、これならいいな!と感じたので、「It looks fine.」と答えたところ、彼の表情が曇り、「So… should I change something?」と返されました。
彼にとって私の言葉が「特に問題はないけれど、改善の余地があるかもしれない。」「完璧ではないけど、まあ許容範囲かな。」と捉えてしまっており、「本当は何か不満があるのかな…?」と、不安に感じてしまいます。同様の意味で「Not bad」も挙げられます。
この場合実際の「いいね」のニュアンスで並べると
| 表現 | 実際のニュアンス | 受け取り側の印象 |
| It’s fine. | 問題はないが、あまり積極的ではない | 改善が必要か不安になる |
| It’s good. | 良い。比較的ポジティブ | 悪くないけど、特別素晴らしいわけでもない |
| That’s good! | 素晴らしい!積極的な肯定 | とても良く評価されている |
| That’s excellent! | 非常に素晴らしい、最高! | 非常に高い評価 |
「Fine」はこの中で最も弱く、「最低限の合格ライン」という印象です。本当に良いと積極的に伝えたい場合は、感情を込めて「That’s excellent!」を使うほうが適切です。
Issue (課題ではなく・・・?)
日本のビジネスでは「イシュー」という言葉は「取り組むべきテーマ」「解決すべき課題」程度の軽い意味で頻繁に使用されています。これは前向きで「解決の余地があるテーマ」という感覚で使われます。
一方、英語のネイティブスピーカーにとっての「Issue」は、『課題』というよりも『問題』あるいは『トラブル』に近いややネガティブで深刻な響きを伴います。

また、emailの標題において、『〜〜〜の件』という書き出しを日本語ではよくします。私も当初、仕事を初めて英語レター(!)を作成した際、そう先輩から教わりました。最近見ないので「私だけの問題かも・・・。仲の良い同僚から指摘されるまで、結構長い間続けてましたね。
例えば、日本語で「顧客登録の件」と記すつもりで、Customer’s registration issue、とやっていました。これはネイティブにとって『顧客登録に対して発生している問題』と捉えられてしまいます。
一方、「軽い課題」や「将来的に改善したいポイント」を英語で伝える場合は、「Issue」ではなく次のような表現を使うほうが誤解を防げます。
- Topic
- Subject
- Point to address
- Area to improve
- 「We have a few points to address next quarter.」
(次の四半期で取り組むべき課題があります。) - 「One area we can improve is customer response time.」
(顧客対応時間が一つの課題です。)
これらを使うことで、前向きで建設的なニュアンスを伝えることができます。
この様に英語の「Issue」は日本語で使う感覚よりも重いニュアンスがあます。ビジネスの場では、誤解や無用な緊張を避けるため、状況や緊急性に応じて別の表現を積極的に活用しましょう。
Challenge(難易度は・・・?)
日本語の「チャレンジ」と言えば、「積極的に挑戦する」「前向きに取り組む」という、非常にポジティブで意欲的な響きがあります。そのため日本人は、「Challenge」をビジネスの場面でも同じように使うことが多いです。
しかし実際のビジネス英語において、「Challenge」はポジティブな要素を含みつつも、「難易度が高い」「達成困難」という、ネガティブで困難を示すニュアンスを強く持っています。
例えば、「It’s a challenge.」という英語表現も、日本語の感覚では、「やりがいがある!挑戦しよう!」となりますが、英語では「実際はかなり難しい。達成は簡単ではない」と感じられています。「Very difficult」に近い感覚です。
Challenegと一緒に使われる動詞に「face(直面する)」があります。「We are facing the challenges」について、日本語の感覚では「課題に取り組んでいる」という印象ですが、欧米メンバーだと「深刻な障害・困難な壁に直面している状況」の意味合いが強いです。
日本人が「Challenge」のつもりで使う場合、実際には「Opportunity(機会)」の方が適切な場合もあります。同じ取り組み対象でも「積極的で前向きな挑戦の機会」というニュアンスが強くなります。キャリアアップや新市場開拓に対する意欲も伴います。
まとめると、英語の「Challenge」は決して単純なポジティブな意味の「挑戦」ではなく、実際は「難しさ・厳しさ」を強調する言葉です。
- ポジティブで積極的な挑戦:Opportunity
- 努力が必要で困難な課題:Challenge
- 非常に難しい、達成不可能に近い:Real challenge, Difficult
日本語の「チャレンジ」の感覚だけで「Challenge」を使うと、「達成困難」といったネガティブな印象を与える可能性があるため、意識的に「Opportunity」などを使い分けることが重要です。
Challengeについては、以下の記事でも詳しく紹介しています。
まとめ
ビジネス英語では、日本語の感覚で言葉を選ぶと、意図しないニュアンスになってしまうことがあります。コミュニケーションにおけるニュアンスの違いをしっかり理解し、正確な英語表現を選ぶことで、グローバルなビジネスシーンでの誤解を防ぎましょう。特に重要な場面では、明確で積極的な表現を使うことを心がけてください。
- 「Interesting」はポジティブともネガティブとも取れる文字通り「微妙な」表現
- 「Understand」(わかる)と「Agree」(賛成)は別物
- 「Consider」は、実行を伴う可能性は低い
- 「Suggest」を上司が使うと、「推奨」よりも「事実上の指示」
- 「Fine」は単なるOKであり、ポジティブな評価とは限らない
- 「Issue」は、「軽い課題」よりは「解決すべき問題」
- 「Challenge」の難易度は日本よりも高い
実際のコミュニケーションでは、言葉だけでなく、相手の反応や文化的な違いも考慮することが大切です。

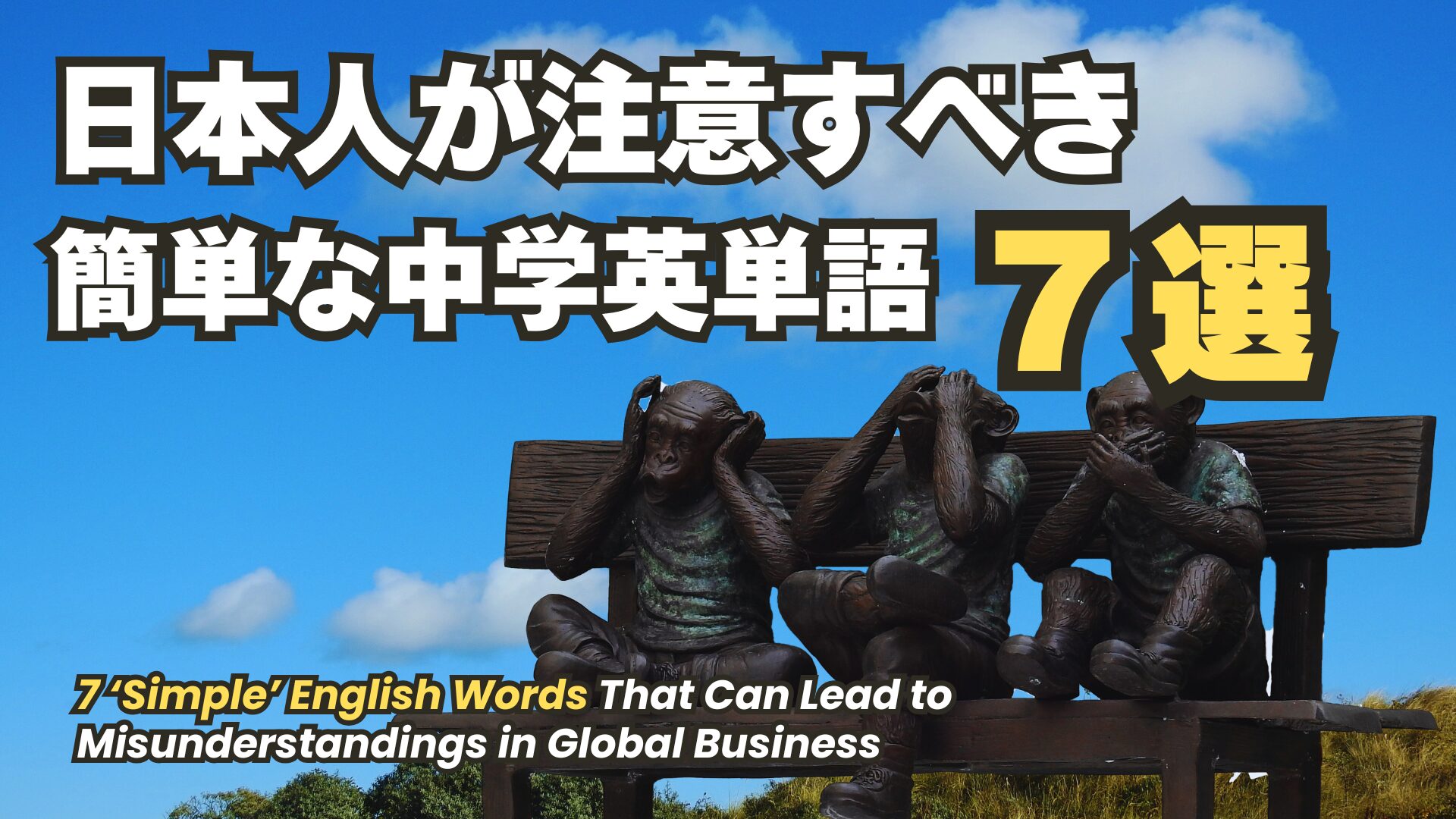

コメント