海外でマネージャーとして働くとき、現地の人事制度や法律、そして文化的な価値観の違いを正しく理解しているかどうかは、組織運営の成否を左右します。「知らなかった」では済まされない落とし穴が、実は日常の中に数多く潜んでいます。
今回は、私自身がグローバルチームを率いる中で経験した、ある小さな失言がきっかけとなった苦い学びを共有します。
はじめに:何気ない説明が生んだ誤解(背景と経緯)
Aさんとの業務の様子
数年前、私が担当していたグローバルチームの再編に関連して、ある米国人女性社員、Aさんの部署異動を検討する場面がありました。
彼女は別の部門から私たちのチームに加わったばかりで、仕事に対する姿勢は真面目でしたが、私たちのチームが求める働き方——特に日本や欧州との連携が求められる不規則な勤務時間——との相性が必ずしも良くはありませんでした。
家庭との両立に苦労している様子も見え隠れし、複数のオンライン会議中に、子どもの声や背景での対応が散見されることもありました。
私自身、当時は“日本的な上司のマインドセット”で、Aさんの生活環境や心身の負担を心配しており、業務への支障以上に、彼女のコンディションが大丈夫か気にかけていた部分もありました。
そんな中、たまたまAさんが以前所属していた部門から「戻ってきてほしい」と声がかかりました。
ちょうどAさんの新たな出産休暇 (Maternity Leave) 申請を受けた矢先だったため、業務はさることながら、彼女のライフスタイルにとっても、問題解消できる好機と判断。もちろん会社にとってもベストな選択だと考え、前向きに異動を進めることにしました。
異動説明での誤解
ところが、異動の説明を直属の部下のBさん(女性マネージャー。異動対象のAさんの直属上司)に行った際、私は不用意にも「子育てや妊娠のこともあるので、Aさんにとってこの異動は望ましいと思う」といった趣旨の発言をしてしまいました。
Bさんはすぐに反応し、「子育てがAさんの異動理由になったのですか?」と再確認してきました。その表情には、言葉にしきれない“違和感”がにじんでいました。
Bさんが当事者ではないにもかかわらず、直属のマネージャーとして、また米国の価値観を理解した立場から、この件のリスクを的確に読み取ってくれたのです。
私は「子育てや妊娠」を異動理由にしたつもりはまったくありません。ただ「よかれと思って」という気持ちが説明の中ににじみ出ていたのは確かです。
私が主旨を再度説明しなおし、誤解に対して謝罪したこと、さらに幸いBさんとは長い信頼関係があったこととで直接的な衝突にはなりませんでした。
Bさんがその場で指摘してくれなかったら、私はAさんとの面談でも同じ様な「よかれ」を説明してそれこそ取り返しのつかない問題となった可能性があります。
一方で、もしBさんに「この人は業務とプライベートを混同する人だ」と思われていたら……。彼女とのこれまで築いてきた関係が、たった一言で崩れていたかもしれない、と思うと、こちらも悔やんでも悔やみきれません。
米国での人事における法的・文化的背景
今振り返ると「Aさんのためによかれと思って」という日本風の「気遣い」が問題でした。

その“よかれ”という思いは、あくまで私個人のものであり、本来はこの異動の理由やその説明とは切り離されるべきものでした。
今回のような場面では、「たとえ気遣いや親心であったとしても、あえて言葉にしない」という姿勢こそが、プロフェッショナルな対応だったと今は考えています。
特に米国では、妊娠・出産・子育てといったプライベートな要素を業務判断に紐づけることは、場合によっては『差別(Discrimination)』とみなされる可能性があります。
特に以下の2つの法律的枠組みは、管理職にとって必須知識です。
1. 妊娠差別禁止法(PDA)とEEOCのガイドライン
- 妊娠・出産・関連の医療条件による差別を禁止。
- 「彼女には育児があるから負担の少ない部署がよい」というのは、たとえ善意でもステレオタイプに基づく判断と見なされる。
- 参考Webpage[EEOC]
2. PWFA(Pregnant Workers Fairness Act)
- 妊娠中や産後の従業員に対し、合理的な配慮(勤務時間の柔軟性、軽作業など)を提供することが義務化。
- 「合理的配慮」は本人が申し出ることで成立し、管理者側から先回りして“配慮”することには慎重さが求められる。
- 参考Webpage [PWFA]
日本との違いと、なぜ誤解が起こるのか
日本では「家庭事情を慮って配慮すること」は良しとされる文化があります。しかし米国では、「業務の正当な理由」以外で異動・評価を決めること自体がリスクを孕みます。
これが私の陥った失敗の根幹にありました。
- プライバシーに関する感度の差:
- 米国では、社員の健康状態、家族構成、宗教、出身地、性的指向など、仕事と直接関係しない個人情報には極めてセンシティブです。
- たとえば「最近疲れてそうだけど体調大丈夫?」「実家がどこなの?」といった日本では当たり前の雑談も、米国では“踏み込みすぎ”と受け取られる可能性があります。
- また、メンタルヘルスに関しても触れるには慎重を要し、本人が明示的に共有しない限り、上司からの関与は避けるのが原則です。
- 管理職が気を利かせたつもりの「宗教上の理由で休みたいかもしれないからシフトを調整しておいた」などの行為も、かえって本人の権利や平等な扱いを損なうとみなされることもあります。

- “正義の平等”への意識:誰かが“特別扱い”されていると他者から見えること自体が問題に。
- 米国では「全員を平等に扱うこと」が組織文化の基本です。たとえ善意からの配慮でも、一人の社員だけが特別に柔軟な働き方や待遇を受けていると見えると、他の社員のモチベーションや公平感に悪影響を与えるリスクがあります。
- 特定の人に対して繰り返し便宜が図られているように見えると、「会社は誰を重視しているのか」という不信や不満が生まれ、チーム全体の雰囲気を損なうことにもつながります。
- さらに、私のように複数の国をまたぐグローバル環境で働く管理職の場合、米国と欧州の労働環境(たとえばバケーション日数や勤務時間への考え方)に違いがあることも、公平性(Fairness)の議論につながることがあります。こうした点については、また別の記事で詳しく取り上げたいと思います。
このような背景を理解していないと、日本的な配慮が裏目に出てしまうのです。
管理職として気をつけたい5つのポイント
- 異動・評価はあくまで業務の事実ベースで伝える
- 私生活の事情には原則、触れない。話題にされたら受け止めるだけにとどめる
- 合理的配慮が必要な場合は、本人との“対話”でニーズを聞く
- 説明内容に迷ったら、HRまたはリーガルに事前相談
- 失言・誤解があれば、できるだけ早く素直に謝る
まとめ:信頼されるリーダーであるために
今回の件を通じて学んだのは、「たとえ善意であっても、説明の言葉を間違えると信頼を損なう」ということです。特に文化や法制度が異なる米国では、言葉の一つひとつが持つ意味が大きく、無意識のうちに相手の価値観や権利を侵害してしまうことがあります。
“配慮”とは、本人が必要としたときに、対話の中で実現するもの。過剰な推測や先回りは、時に相手の尊厳を奪ってしまうのです。
私も多くの失敗から学びました。この記事が、同じように奮闘するあなたの助けになれば嬉しいです。

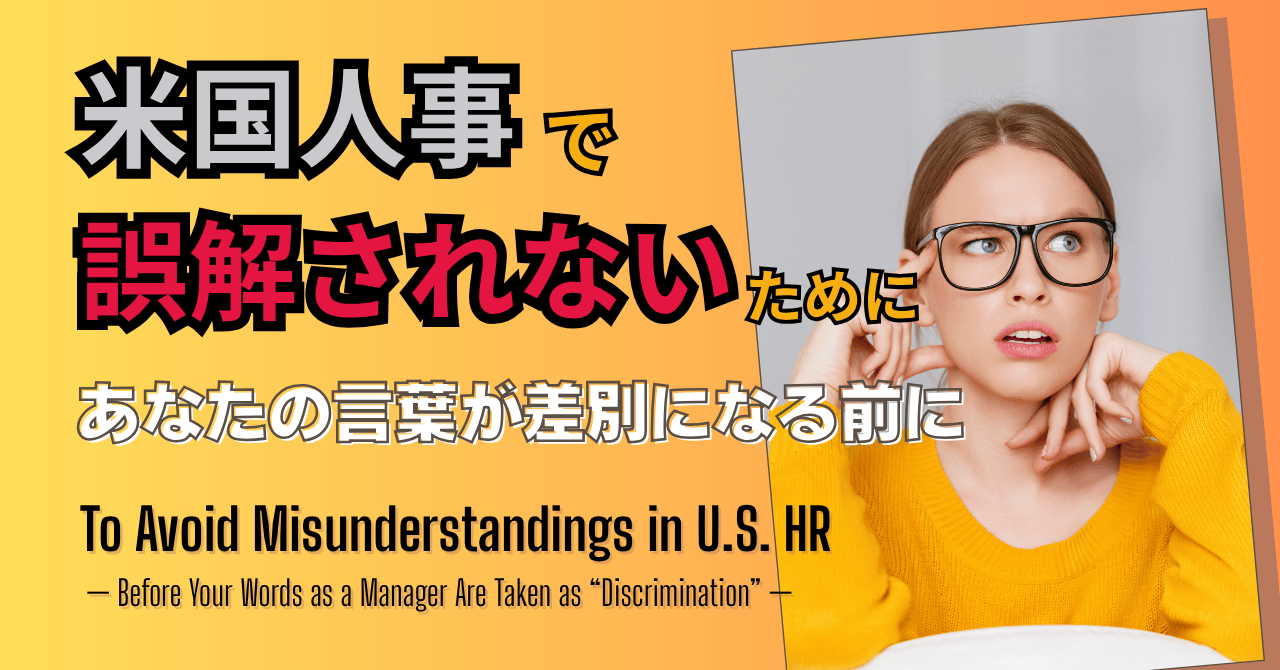
コメント